<本ページはプロモーションが含まれています。>
今回は、息子(中学2年生)が始めた「スタディサプリ」についてお話ししようと思います。
スタディサプリとは?
CMでおなじみの「スタディサプリ」とは、リクルートホールディングスの子会社であるリクルートマーケティングパートナーズが運営しているインターネット予備校のことです。
<以下、スタディサプリ公式サイトより引用>
①プロ講師の授業動画が見放題!
②映像授業は5教科。演習問題は実技を含めた9教科に対応
③厳選予想問題で実際のテストに近い形式で演習ができる。
④定期テスト対策は英数国理社に加え、実技4教科(音楽・美術・技術家庭・保健体育)も対応。
⑤教科書に対応した定期テスト厳選予想問題は、テストに出やすい問題からテストで差がつく応用問題までを収録。
⑥問題が厳選されているから短時間で効率的に学習できる。
⑦選択式だけでなく記述式や語句を解答する問題が出題されるので、実際の定期テストに近い実戦的な演習問題になっている。
⑧暗記マスターはテストに出やすい語句を厳選。手軽に暗記の学習ができる。
今から3カ月前
私には、中学2年生の息子がいます。
今からさかのぼること3カ月前。
当時、学校での息子の成績は学年全体で上位10%にようやく入ったところでした。
彼なりに勉強に打ち込んではいたので、中学になって1年の夏の時点では自学自習の習慣がしっかりついて、2年生になっても少しずつですが、成績は確実に上がってきていました。ただし、テストでは毎回ケアレスミスが目立ち、まずはこれを無くすことが大きな課題でした。
平日は、部活から帰ってくるのが夕方18時頃。それから入浴と食事を済ませ、20時~0時までの4時間が勉強時間。
宿題が多いときは午前1時を過ぎてからの就寝ということも多く、勉強時間はしっかりとっているけれど、その結果を最大限発揮できていないという状況でした。
そんなカツカツな毎日を送りながら中2の秋に入った頃、息子が「僕もそろそろ塾にも行った方がいいんじゃないか?」と言い出しました。
理由を聞いてみると・・・
国語と数学が苦手なのと、まわりの生徒の半分以上が塾に行ってるというのが理由でした。息子なりにプレッシャーを感じていたようです。
塾に通わせるか否か
とはいうものの。
そもそも時間的に毎日カツカツ。部活は続ける前提で今の生活に塾を追加してしまっては、とてもじゃないけれどこなしきれない・・・
となると、家での勉強の時間を削るしかありません。塾で教わるということは良いのですが、せっかく自学自習の習慣が身についたのに、そこを削っていいものか・・・
とりあえず、本人が塾に通いたいというので了承はしたものの、親としても悶々とする日々が続いたのでした。
塾以外の選択肢「スタディサプリ」
そして、1週間経った頃。
「塾通いは時間的に無理!」と判断した妻が提案してきたものがありました。
それが「スタディサプリ」でした。
口コミもしっかり調べてみると、なかなかの評価。
幸いなことに、14日間無料体験があったので、先ずはお試しで始めてみました。
それからというもの・・・
勉強するときは左手にスマホが当たり前 になった息子。
昭和世代の私からすると、スマホ片手に勉強している息子の姿はちょっと違和感がありました。「これで本当に成績が上がるのか?」と半信半疑。
14日間の無料体験を終えて
でも、無料体験を終えた時点で、息子に聞いてみると・・・
「講師の解説が、とてもかりやすい!」
「自分でやってみてわからなかった問題は、スタディサプリの解説でカバー出来ている」
と、手ごたえはまずまず。
私としては、あまり期待していなかったスタディサプリ。
でも、息子の反応が思いのほか良かったので、そのまま継続することにしたのでした。
さらに2カ月やってみてた結果は・・・
さて、スタディサプリをやって2カ月たった頃、ちょうど期末テストがありました。
その結果は・・・
学年全体の 上位10%ライン から 上位2%ライン に上がりました!
苦手だった国語と数学をしっかり上げながら、得意な英語と社会もそれまで以上の点数を取ることが出来ました。ちなみに、英語はケアレスミスが少なくなったことで、結果として学年1位となり、ここで一気に全体順位を上げることが出来ました。
何よりも良かったことは、今までの生活スタイルを変えることなく、無理なく成績を上げることが出来たことでした。
この経験を通して実感したことは、「自学自習」ができる子の場合、スタディサプリはかなり有効なツールだということ。
ということで、私としてもスタディサプリにがぜん興味がわき、あらためて調べてみました。
スタディサプリについては、ブログやYouTubeなどで数多く取り上げられています。特に塾の講師の方が解説しているものは参考になりました。今回は、その一部を私の考察を踏まえてご紹介したいと思います。
スタディサプリの良い点
①住んでいる場所を問わず、ハイレベルの授業を体験できる!
私も実際に授業動画をいくつか見ましたが、講師の皆さんとても話が上手です。話の組み立てが絶妙で滑舌も良く、何よりも要約力が素晴らしい!この内容を片田舎の自宅に居ながらにして体験できることは、本当にすごい事です。ネット環境が整った恩恵だとつくづく思いました。
子どもの学習レベルに合わせて、オンラインで個別指導を受けるプランや、授業動画を見て自習するプランなどから選べます。
②移動や待つ時間がない
スタディサプリと塾の大きな違いとしては、受講するための移動がないこと。ここはかなり大きい!親としても送り迎えの必要が無いのは、かなりありがたい。移動時間や待ち時間を、そのまま学習の時間に充てられますので、子どもも親もかなりの負担を軽減できます。
③苦手な科目は、授業動画を繰り返し見て落とし込める
これ、おすすめのポイントです!
実際に利用してみて実感しました。頭に入るまで何度も見る事が出来る。シンプルですが、かなり効果的です。ちなみに、うちの息子はオンライン個別指導ではなく、問題を解いて授業動画だけを利用できるプランですが、これだけでもかなり効果があったということは、先の期末テストの結果からお分かりいただけると思います。
スタディサプリ以前に重要なこと
それは「自学自習」が身についていること。
まず、一度自分でやってみて、それでもわからない問題についてだけ、スタディサプリの解説を見る。このプロセスが重要とのこと。この点も実際に利用してみてその通りだと実感しています。
自学自習が出来ていない状態でスタディサプリを利用しても、ほとんどの場合、面白い授業を見たというだけで終わってしまします。
授業を受けたことでやった感があっても、しっかり落とし込めていないので、肝心なテストで結果が出せないわけです。
この点については、仕事でも一緒だと思います。物事を習得するプロセスとしては、座学でインプットした後に、とにかくアウトプットすることが大切です。インプットするばかりでは、実戦で使えません。
ある塾の先生がおっしゃっていたのですが、
「授業2割:自習8割」
これくらいの割合が基本とのこと。納得です!
スタディサプリを利用する上での注意点
時間の浪費に注意!
先にもお話ししましたが、スタディサプリの講師の皆さんは、とにかく話が上手です。大人の私が見ていても面白い!
ただし、面白いだけに、ついつい必要ない箇所まで見てしまうわけです。まさに、休みの日のYouTubeやネットフリックス状態。ここは要注意です。
一番の課題
大前提としては、
①自学自習が出来ていること。
②自分が苦手なポイントが自覚できていること。
③苦手なポイントだけをスタディサプリでカバーする。
これがスタディサプリの正しい使い方だと思います。
まあ、塾に通っても同じ現象は起こりえますけどね。むしろ授業を途中退席出来ない分やっかいかもしれません。
ただし一方で、一般的な塾の良さもあると思います。それは「勉強をする熱気」。
子どもが自宅で自学自習をする場合、この「勉強をする熱気」を、自分自身で作り維持しなければいけません。
つまり、モチベーションを含めた「自己管理」が一番の課題だと思います。もちろん、これには親の協力も不可欠です。
スタディサプリを有効活用する5つのポイント
要は使い方次第ですので、ポイントを5つまとめてみました。
①スタディサプリを始める前に、まず子どもの現在地を把握する。
まず、「どの強化が苦手で、どの箇所を頑張れば結果が出やすいのか?」を把握する必要があります。
②その上で、科目別に必要に応じてギャップを埋めていく。
次に、結果を出しやすい科目を中心に力を入れる配分を決めましょう。
③ポイントは伸びしろの大きいところを攻める。
最初から全部は無理です!結果が出ないと達成感も得られませんので長続きしません。ですから、まずは1~2教科だけに集中して、結果が出にくい科目は後回しにするのもありだと思います。まずは、「頑張ったら結果が出る!」という成功体験を経験させてあげることが大切です。
④スタディサプリの定着度を定期的にチェックする。
スタディサプリが合っているかどうかを、注意深く見てあげてください。しっかり取り組めないのであれば、続けても意味ありません。その場合は、時間とお金を他の事に充てるべきです。
⑤成果を踏まえて次の課題を設定する。
これをしっかり繰り返すことが重要です!前に進み続けるには、課題設定をしっかりしましょう。「3ヵ月後の期末テストで、数学と国語だけは学年平均+20点以上をとる」などの具体的な課題設定がないと達成感が得られないので、長続きしません。
まとめ
今回は、「スタディサプリの効果は?息子(中2)が2ヶ月利用してみた結果は・・・」
というタイトルで書かせていただきました。いかがでしたでしょうか。
私の息子の場合、スタディサプリを利用したことで、苦手だった国語と数学の成績が上がり、2か月後のテストで学年上位20%から6%以内に入るまで成績が上がりました。
何よりも良かったことは、今までの生活スタイルを変えることなく、無理なく成績を上げることが出来たことでした。
この経験を通じて実感したことは、「自学自習」ができる子の場合、スタディサプリはかなり有効なツールだということ。
そして、スタディサプリを始めるにあたって大切なことは、子どもが「どの教科が苦手で、更にどの箇所を頑張れば結果が出やすいのか?」ということを、しっかっり把握すること。
その上で、伸びしろの大きい科目から取り組む。
あとは、結果を見ながら定着度をチェックして、続けられそうなら続ける。無理そうなら別の手段を探す。という具合で進めて頂ければと思います。
それでは、今回はこの辺で。
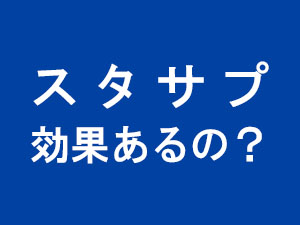

コメント